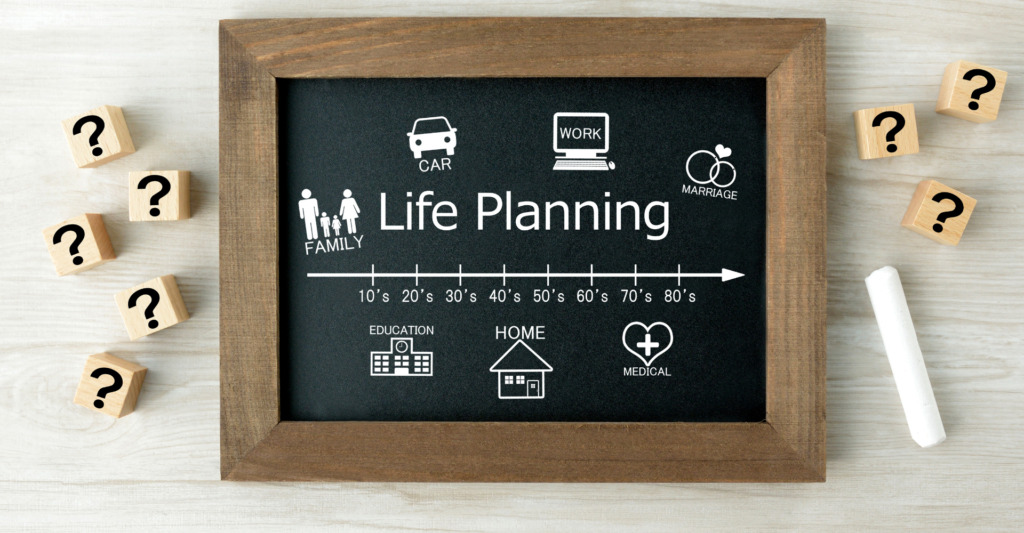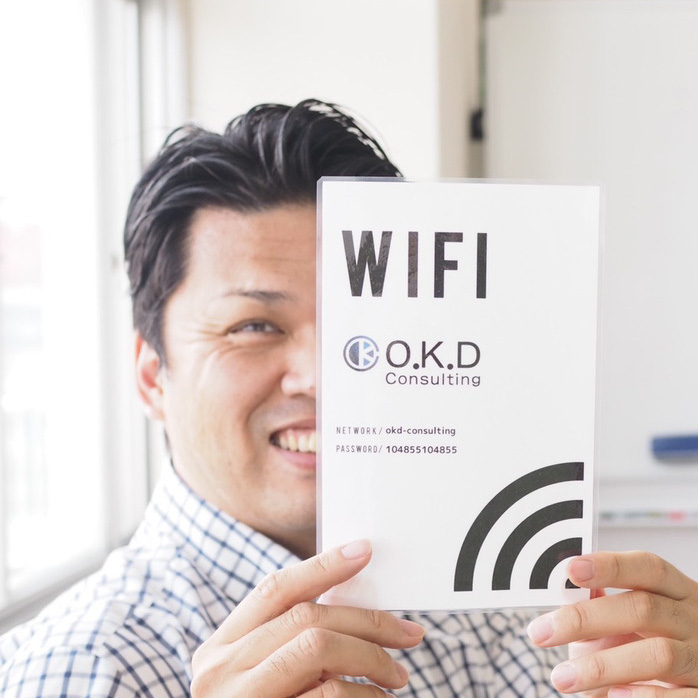▼動画でも土地契約の失敗事例をご紹介しています▼
\土地契約で損しないために!/
無料個別相談・勉強会実施中
「重要事項説明書って何?」「この土地、買って大丈夫?」「失敗事例を先に知りたい」
そんな方向けに、おうち購入研究所アドバイザーが丁寧にサポートします!
- 土地契約で「絶対にやってはいけない落とし穴」とは?
- ハウスメーカー同席の実際の失敗・成功事例が知りたい
- 今、悩んでいる契約内容をプロに見てほしい
※「この記事を見た」と伝えるとスムーズです。
「この土地、本当に大丈夫?」「契約書って難しすぎて意味が分からない…」
不動産会社の言うがままに契約を進めた結果、家が建てられない・予算オーバー・ローンが通らないといったトラブルが後を絶ちません。
この記事では、土地契約前に絶対に確認すべき7つの落とし穴を、中立FPの7年の現場経験に基づき実例交えて解説します。
土地探しで最も危険なのは「建てられない土地」契約前に要チェック
土地探しにおいて最も大きな落とし穴が「家が建てられない土地ではないか?」です。
これには複数のPOINTがあります。
たとえば
建築基準法で定められた接道義務を満たしていない土地(幅4m以上の道路に2m以上接していない土地)は、
基本的に建物の新築や再建築ができません。
また、敷地内にセットバック(道路の中心線から一定距離を下げた部分)の必要がある場合も、建築可能な面積が減り、希望の間取りや駐車場が確保できなくなるケースがあります。
さらに注意したいのが上下水道やガスのインフラ状況です。
一見して何も問題がなさそうに見える土地でも、上下水道の本管が敷地前まで来ていなければ引込工事が必要になり、
場合によっては数十万円〜100万円以上の費用がかかることも。
地盤の状況も見落とせません。
地盤が軟弱な場合、改良工事費が高額になることがあり、
これも数十万円から時には200万円以上かかることもあります。
そして最も危険なのが「再建築不可物件」と呼ばれる土地。
これは一度建物を壊してしまうと、もう二度と建物を建てられないケースです。
多くの場合、古家付きで販売されており「リノベーションすれば大丈夫です」といった営業トークに惑わされがちですが、ローンが通らなかったり、売却時に大幅な価格下落に見舞われるなど、リスクが非常に高いです。
これらの条件は、不動産会社が教えてくれるとは限りません。
むしろ「早く決断してください」と契約を急かされるケースも。
だからこそ、契約前に建築士など専門家に確認してもらい、
「この土地に希望の家が建てられるか」をチェックすることが不可欠です。
たとえ好立地で価格が手ごろでも、「建てられない土地」は“買ってはいけない土地”なのです。
不動産営業が言わない「建築条件付き土地」の落とし穴
「建築条件付き土地」とは、土地の売買契約後、
一定期間内に指定された建築会社と住宅建築請負契約を結ぶことが条件となっている土地のことです。
一見すると「土地と建物がセットで安心」「すぐに家が建てられる」といった
メリットが強調されがちですが、実際には多くの落とし穴が存在します。
まず、建築会社が自由に選べないため、
施主にとって理想の家を建てる自由度が大きく制限されてしまいます。
例えば「間取りをこうしたい」「この設備を使いたい」という要望があっても、
指定業者の仕様や標準プランの範囲内でしか対応できず、
自由設計とは名ばかりの場合も多くあります。。。
また、契約を急かされることも多く、「○月○日までに契約しないと他の人にまわってしまいます・・・」
といった営業トークで、じっくり検討する時間を奪われてしまうケースもあります。
契約後に「やっぱりこの業者では建てたくない」となっても、
土地契約をしてしまうと簡単にはキャンセルできません。
さらに注意すべきはコストの構造です。
土地の販売価格が相場より安く設定されていることが多いですが、
それは建物費用で利益を補うため。
いざ建築の打ち合わせが始まると、標準仕様では物足りずオプション追加が続き、
結果的に「土地+建物の総額」で見ると割高になることが少なくありません。
最終的に坪単価が上昇し、予算を大きくオーバーしてしまう方も多いのです。
また、指定業者の技術力やアフターサービス、施工実績などが不明瞭なまま契約が進むこともあります。
「地元の工務店で安心」と思っていたら、実は下請け任せで品質にバラつきがある、といった事例も。
こうしたリスクは、不動産営業からは積極的に語られません。
営業マンの目的は「土地を売ること」や「自社施工で利益を出すこと」であって、
施主の理想を叶えることではない場合もあるのです。
建築条件付き土地を検討する際には、
「なぜこの土地は安いのか?」
「建築業者の指定が本当に自分にとってベストなのか?」を冷静に判断しなければなりません。
できれば専門家と一緒に検討を進めることで、営業トークに流されず、自分にとって本当に納得できる家づくりが実現できます。
目先の価格や立地の良さに惑わされず、総合的な視点で判断することが大切です。
重要事項説明書に書かれた“ヤバい文言” BEST5
土地契約の際に交付される「重要事項説明書」には、普段の生活では見かけない専門用語がずらりと並んでいます。
しかし、その中に“読まずにサインしてしまうと人生を左右する重大なリスク”が潜んでいることを知っている人は少数です。
ここでは、OKDが現場でよく見かける「見逃すとヤバい文言」を5つご紹介。
なぜそれが危険なのかを実例ベースで解説します!
①「市街化調整区域」:これは、原則として家を建てることができないエリアです。
特例が認められる場合もありますが、それには厳しい条件があり、誰でも建築可能というわけではありません。
不動産会社が「大丈夫ですよ」と軽く言っていたのに、
実際には建築許可が下りず、土地だけ買ってどうにもできなかったというケースも存在します。
②「埋蔵文化財包蔵地」:この文言があると、建築時に教育委員会などへの届出が必要になり、調査費用や工期の遅延が発生します。
調査結果によっては発掘が必要になり、数十万円以上の追加費用がかかることもあります。
最悪の場合、家の建築が数ヶ月単位でストップする可能性も。
③「土壌汚染」や「地歴に関する記録あり」:過去に工場や産廃処分場だった土地などは、土壌汚染の可能性があります。
土壌汚染対策法に基づき浄化や封じ込め工事が求められることがあり、その費用は施主負担になることも。
ローンが下りない原因にもなるため、かなり要注意です。
④「道路種別:私道」かつ「負担金あり」:一見問題なさそうな道路表記ですが、
私道の場合は通行権が法的に保証されていなかったり、将来のメンテナンス費用を請求されることも。
さらに他人の土地を通行していると、売買や建て替え時に大きなトラブルになる可能性があります。
⑤「建築協定」「地区計画あり」:建ぺい率・容積率以外にも、
建物の高さ制限・色・素材・駐車場の設置条件など細かいルールが定められている場合があります。
思っていたようなデザインの家が建てられない、外構が条件に合わず再設計になるといった事例も。
これらの文言は、重要事項説明書に小さく、そしてサラッと書かれていることが多いです。
しかも、説明する宅建士も「一応義務として読み上げる」程度で、詳細な説明は省略されることが珍しくありません。
契約前にこの説明書をもらって第三者の専門家(FPや建築士など)にチェックしてもらうことで、失敗を未然に防ぐことができます。
とくに初めて土地を買う人にとっては、“説明書は契約書以上に重要”だと覚えておいてください。
契約日を急かされることのリスク
土地契約は買付申込書を入れるとすぐに契約となります。早ければ明日、なんてことも。
一般的には申し込みを入れてから一週間後になります。
契約日に指定の契約場所に行くとその時点で初めて契約書や重要事項説明書を提示され、
その場で2時間ほどの読み合わせを受けた後に、すぐ署名・捺印を求められるという流れになります。
しかし、これは非常に危険です。
なぜなら、その場で契約内容をすべて正確に理解し、重要なリスクを見抜くのは不可能に近いからです。
重要事項説明書や契約書は、専門的な用語や法的な表現が多数含まれており、
不動産に詳しくない一般の方にとっては非常に分かりづらいものです。
仮に説明があったとしても
「はい、次にこちらが都市計画法に関する項目です」などと流れ作業のように読み上げられるだけで、
内容の意味を丁寧に説明してくれるケースは稀です。
さらに、「気になることがあればご質問ください」と言われても、
何が重要か分からない状態では質問すらできません。
そもそも契約とは、双方が納得したうえで合意するものであり、「理解できないままサインする」という行為は、
後々のトラブルを自ら招くようなものです。
契約日を急かす営業には、特に注意が必要です。
理想的なのは、契約書や重要事項説明書を事前に受け取り、2〜3日かけてじっくり読み込んだうえで、
分からない部分は専門家に相談しながら進めることです。
場合によっては、不動産会社に「契約書と説明書を先にいただきたい」と伝えるだけでも、相手の対応スタンスが見えてきます。
それでも資料の提供を渋るようであれば、その会社は信頼に値しないと判断するひとつの材料になります。
また、当日サインを迫られた際に「一度持ち帰って検討させてください」と言っても問題ありません。
法律的にも、契約前であれば拒否はまったく正当な権利です。
無理にその場でサインしてしまうと、「契約書に署名されていますよね?」という言葉で、
後の交渉が非常に不利になります。特に初めてのマイホーム購入であれば、慎重すぎるくらいがちょうど良いのです。
土地契約は、多くの方にとって一生に一度の大きな取引です。
その大切な場面で「なんとなく」でサインすることは、絶対に避けるべきです。
冷静に・慎重に・第三者の力も借りて、自分にとって本当に納得できる契約に臨みましょう。
たった一つのサインが、人生を大きく左右する可能性があるのです。
土地契約にかかる「見えない費用」
土地の価格は表向き「1,500万円」などと明記されていますが、
実際にその土地に家を建て、住み始めるまでには、様々な“見えない費用”が発生します。
これらを事前に把握せずに契約してしまうと、「え?こんなにかかるの?」と後になって驚くことになります。
そしてそれは、資金計画のズレ=予算オーバーを引き起こし、
最悪の場合、家づくりそのものを見直さなければいけない事態に繋がるのです。
まず最も代表的なのが「仲介手数料」です。
不動産会社を通して土地を購入する場合、仲介手数料として
「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限としてかかります。
1,500万円の土地であれば561,000円費用です。
これを見落としている方は非常に多く、資金計画に入っていないことで後から慌てる原因になります。
さらに見逃してはいけないのが、
「住宅ローン斡旋費用」や「ローン事務代行手数料」といった不明瞭な名目で請求される費用です。
これらは特に建売業者や一部の不動産会社で見られ、
「ローンの手続きはこちらで代行します」という名目で数万円〜数十万円を請求されることがあります。
しかし、住宅ローンの申請は本来、買主が自分で金融機関に行うことができますし、
そもそも無料で手続きが可能なケースがほとんどです。
「事務手数料」や「ローン代行費」などと書かれた請求書を見たときには、
「それは本当に必要な費用か?」「内容は明確か?」を必ず確認してください。
中には、その費用が営業マンのインセンティブになっているだけで、
実際にはほとんどの業務を金融機関が行っているというケースもあります。
仮にサポートが必要だとしても、料金体系が明確でないものには注意が必要です。
契約の際に含まれるすべての費用項目に対して、
「なぜ必要なのか」「他に選択肢はないのか」を一つひとつ確認していくことが、安心の第一歩です。
不要な費用を削れば、その分家づくりの本質的な部分にお金をかけることができます。
ローン関係の費用は特にグレーゾーンが多いため、
FPや金融機関にも相談しながら進めることをおすすめします。
次に「上下水道の引込工事費」。古い土地や造成前の分譲地などでは、
水道が敷地内まで引かれておらず、道路から引き込む工事が必要になります。
この費用は数十万円〜100万円以上かかるケースもあり、自治体や土地の条件によって異なります。
都市ガスを使う場合はガスの引き込み費用も発生することがあります。
さらに見落とされがちなのが「地盤調査・改良費用」です。
建物を建てる前に、地盤がどれだけ強いかを調査するのが一般的ですが、地盤が軟弱だった場合には補強工事(地盤改良)が必要です。
これも数十万円〜200万円前後の大きな費用になることがあり、
土地価格の安さに惹かれて購入した結果、
補強費用が想定外だったという声もよく聞きます。
その他にも「境界確定費用」「測量費用」「外構工事費(門・塀・駐車場)」「登記費用」「火災保険料」など、
積み重ねると軽く数百万円になることもあります。
特に境界が曖昧な土地は、後々近隣とのトラブルになる可能性があるため、
事前に確定しておく必要があります。この費用も土地購入者の負担になる場合があります。
これらの費用は、不動産会社や営業マンがあえて詳しく説明しないことも多く、
「土地代だけで済む」と誤解している方が非常に多いです。
だからこそ、契約前に専門家と一緒にかかってくる費用を確認し、
トータルでいくらかかるのかを“見える化”することが非常に重要なのです。
家づくりは「建物だけ」ではありません。
土地+見えない費用+建物+諸費用の総額で判断しなければ、安心して住宅ローンも組めません。
最後に重要なのは、これらの費用を「いつ・いくら・誰が払うのか」を明確にすることです。
タイミングによっては一時的に現金が必要になる場面もあり、資金繰りのトラブルにも繋がりかねません。
資金計画の精度が、後悔しない家づくりを支えるのです。
住宅ローンが通らない土地とは?
住宅ローンは、どのような土地に対しても必ず融資が下りるわけではありません。
銀行や金融機関は土地や建物に担保価値があるかどうかを重視します。
そのため、担保評価が著しく低いと判断される土地は、
たとえ購入希望者に十分な年収や信用力があっても「土地が原因で審査落ち」になることがあるのです。
ここでは、特に注意すべき「ローンが通りにくい土地」の特徴について解説します。
まず筆頭に挙げられるのが「再建築不可」の土地です。
これは建築基準法で定められた接道義務(原則として幅4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしていないため、
現在ある建物を壊すと新たな建築ができなくなるという制限付きの土地です。
このような土地は銀行にとって
「万が一返済が滞った場合に、売っても価値がつかない=担保としてリスクが高い」
と判断されるため、融資に非常に慎重になります。
次に注意したいのが「借地権付きの土地」。
これは土地の所有者が第三者(地主)であり、買主はその土地を借りて建物を建てるという形になります。
借地契約は法律上の取り決めが多く、更新や契約条件のリスクがあるため、
これも金融機関によっては敬遠されがちです。
加えて、地代の支払いが発生するため、毎月の返済計画にも影響を与えます。
「違法建築が存在する土地」も要注意です。
たとえば建ぺい率や容積率をオーバーした建物がすでに建っている土地では、
その建物の存在自体が法的にグレー、あるいはアウトであるため、ローンを組む際に建物評価がつかず、
結果的に土地の評価も下がってしまいます。
このような物件に対しては、金融機関が「建て替え計画前提なら可」と条件をつけることもありますが、
それには追加の審査や手続きが必要となり、
時間も手間もかかります。
また、「旗竿地(はたざおち)」や「道路に接していない土地」など、
形状や立地条件に問題のある土地も評価が下がりやすくなります。
極端に狭い接道部分しかない場合や、近隣に嫌悪施設(ごみ処理場や墓地など)がある場合も、
担保価値に影響が出る可能性があります。
購入者が気に入っても、金融機関が「売却しにくい土地」と判断すれば、融資は非常に厳しくなるのです。
このように、土地そのものが理由で住宅ローン審査に落ちるということは現実に起きています。
しかも、その事実を不動産営業がきちんと説明してくれるとは限りません。
「この土地は人気ですよ」「急がないと他の方に取られてしまいます」
といった営業トークに押されて契約を急いでしまい、
後からローンが否決されるというのは避けなければならない事態です。
だからこそ、土地購入を検討する際には、
あらかじめ「この土地でローンが通るかどうか」を確認することが非常に重要です。
具体的には、購入前に住宅ローン事前審査を行い、物件情報を添えて金融機関に評価してもらう。
または、信頼できる専門家に相談し、「この土地に問題はないか」
を第三者の視点でチェックしてもらうことも有効です。
住宅ローンの可否は、人生設計を左右する大きな要素です。
せっかく希望に合った土地が見つかっても、ローンが通らなければ意味がありません。
「気に入った土地=買っていい土地」ではないという視点を持ち、
冷静に判断することが、後悔のない家づくりの第一歩です。
土地契約こそ「第三者同席」が第一条件
土地契約は、不動産の売主と買主、そして仲介業者という3者によって進行するのが一般的です。
しかし、この中に買主側の立場に立ってくれる専門家がいないと、圧倒的に情報格差が生まれます。
不動産業者は「中立の立場」と言いながら、
実際には売主側の利益を優先して動くケースが多く、
買主にとって不利な情報をわざわざ強調して説明することは稀です。
そこで必要になるのが「第三者の専門家の同席」です。
ここでいう第三者とは、買主の味方として動いてくれる弊社のような専門家、または宅建士などです。
(弊社には宅建士も所属しております。)
弊社は契約書や重要事項説明書の中に含まれるリスクや不明点を、
買主の立場から見つけ出し、適切な助言をさせていただいております。
不動産の専門用語に慣れていない一般の方が、自分だけで読み解くのはほぼ不可能だからです。
たとえば
「接道義務を満たしていない可能性がある」
「上下水道の引込費用がかかりそう」
「将来的にリスクのある物件」といった内容は、
契約書の文言の中では非常に分かりづらく書かれていることが多いですが、
第三者の専門家がいれば、契約前に「この条件には注意が必要です」と明言できます。
それにより、不利な契約を避けることができますし、
場合によっては交渉の材料にもなります。
また、感情的な流れで契約を急かされる場面でも、
第三者が冷静なブレーキ役となります。
「今申し込みをしないと買えなくなりますよ」といった営業トークが展開された際も、
第三者の専門家がいれば「一度持ち帰って冷静に判断しましょう」とアドバイスできます。
契約は一度締結すると取り消しが困難になるため、
その判断を誤らないためにも“冷静な他人の目”は非常に重要なのです。
特に初めて家を買う方や、不動産の知識が少ない方ほど、
第三者の同席が大きな助けになります。
「分からないことをその場で質問できる安心感」「自分に代わってチェックしてくれる存在」は、契約の場面で想像以上に心強いものです。
第三者がいることで、不動産業者の態度が変わることもあり、
丁寧な説明や条件交渉の姿勢を見せるようになるケースも少なくありません。
土地契約とは、「人生で最も高い買い物」にあたる大きな決断です。
後悔しないためには、「知識のある人を味方につける」ことが最も確実な方法です。
不動産業者の説明を鵜呑みにせず、中立な立場で見てくれる第三者とともに、納得のいく契約を目指しましょう。
たった一人の同席が、あなたの未来を大きく守ってくれるかもしれません。
\土地契約で失敗したくない人へ!/
無料個別相談・勉強会実施中
「重要事項説明書って何?」「この土地、買って大丈夫?」
そんな方向けに、おうち購入研究所アドバイザーが詳しくサポートします!
※「この記事を見た」と伝えるとスムーズです。